教員インタビュー
- yaku*躍*netホーム
- 教員インタビュー
- 吉田先生
教員生活をインタビュー
学校での生活やプライベートまで・・・
吉田先生(以下、吉)、インタビュー(以下、イ)
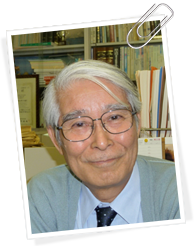
- 所属 : 生化学Ⅱ研究室(微生物代謝学)
- 名前 : 吉田 雄三 先生
- インタビュアー : 渡辺、基村
先生のお好きな食べ物は?
- 吉 : 食べ物で何が好きかと言われると、特に何が好きっていうものはないですね。ローストビーフやビーフシチューのおいしい店があれば、喜んで食べてるけど、絶対にこれが好きでというものはないですね。どちらかというと日本料理より西洋料理のほうが好きだとか、魚より肉の方が好きなどということはあります。
- イ : へぇ。そうなんやぁ(意外!)
- 吉 : あとは、カレーのおいしい所を見つけると嬉しいからカレーも好きなのかもしれない。
- イ : 逆に嫌いな食べ物はありますか?
- 吉 : 魚が嫌いなんです。というかあまり食べられない。
- イ : えぇぇ~!!!魚やったら・・・お寿司とかもダメですか?
- 吉 : ダメです!! お寿司屋さんに行ったらかっぱ巻きとか新香巻きとか・・・
- イ : (笑)安いもので・・・
- 吉 : そう。安物ばっかりで間に合っちゃう(笑)イクラとかウニなんかは敬遠!!
- イ : おいしいのに~・・・(笑)
- 吉 : ねっ!!!(笑)だからローストビーフとかそういうものに・・・
- イ : なるほど?!
休日は何をしてすごしていますか?
- 吉 : 今のような仕事をしていると、めちゃめちゃ忙しくて・・・例えば2月なんて休日が1日もないんです。
- イ : えぇぇ!!
- 吉 : 入学試験などもあるので、休日にどっか行って何かするなど、なかなか出来ない。では、休みに何してるかって聞かれると、家で音楽聴いていたり、カメラ担いでどっかに写真を撮りに行くことなどをしますね。ゴルフに行くとかテニスするとかそういうことはしないです!
- イ : そしたら体を動かすような事はしないということですね。ちなみに音楽ってどんなものを聞くんですか?
- 吉 : 年寄りくさいというかもしれないけれども、クラシックの音楽が好きですね。最近のロックみたいなのもは聞かないです。クラシックだったらだいたいなんでも聴くけども、特にこの曲が好きということはないですね。
- イ : 演奏とかはするんですか?
- 吉 : 残念ながら出来ません。聴くだけです。音楽会に行ったり、CDやレコードを聴いてます。
- イ : オシャレですね!
1年で1・2月が1番忙しいですか?
- 吉 : そういうことではなくて、今年は1・2月にいろいろ学校行事が重なって忙しい。あと、もう1つ大変なのが、薬学が6年制になったから、皆さんの新しい教育を軌道に乗せるためにいろんな準備が学内でも学外でも進んでいるんです。学外実務実習で指導を担当する指導薬剤師さんを養成する仕事なども我々がやらなくてはいけないので、今は特に忙しくなっていますね。
- イ : しばらくの間は忙しいですね。
- 吉 : そうですね。皆さんもこれからおそらく大変だと思うけど・・・(笑)
- イ : あぁぁ(泣)
- 吉 : 今年は特に、旧制度による最後の学年を送り出す一方で、新しい6年制の1期生を5年目に進める準備をやってますから、薬学部の教員は皆忙しいのです。
- イ : 大変ですね(汗)
お勧めスポットは?
- 吉 : 上賀茂神社は知っていますか?
- イ : 知っています!!
- 吉 : あそこは、初詣などで行くと人が沢山いるけれど、それ以外であまり人がいないときに行くと、ものすごく落ち着く場所です。上賀茂神社にはすごく広い芝生があって、その奥に神社があります。そこに行くと落ち着くので好きです。だけどあんまり、遊びに行くところじゃないから、皆さんも何かあってしんどい時に友達と行って、ボーっとすると落ち着くかもしれないですね。日本の神社であそこだけがえらく開けた感じがします。ぜひ行ってみてください!
- イ : はい!!是非行ってみます。
マイブームは?
- 吉 : さっき音楽聴くのが好きって言ったけど、音楽聴くためのオーディオ装置に凝っていたことがありました。最近、ポータブルプレーヤーってあるでしょ?あれでどれくらい良い音が聴けるか、どの装置で聴いたらどんな音がするか、イヤホンはどれがよく聴こえるか・・・、そんなことにハマっています。だから、ポータブルプレーヤーやイヤホンが家にいくつもあります。
- イ : だから授業でも例えでオーディオ機器を使っていらっしゃったんですね!
宝物は?
- 吉 : 難しいですね。実際にずっと持ち歩いているようなモノっていうのはなくって、たとえば、自分に子供がいて、孫がいてっていうのがあるじゃないですか。それがかわいいなぁと思うし大事にしますよね。
- イ : そうですね!
尊敬する人は?
- 吉 : 尊敬する人はたくさんいるけど、有機化学者のウッドワードという人。有機合成化学の発展期に活躍した人で、ビタミンB12の全合成したことで有名です。ウッドワードがある講演で言った言葉に“Plan in detail, then carry it out.”(綿密な計画をたてなさい、それから実行しましょう。)というのがあります。実験科学にとって最も大事なことを簡単な言葉で端的に伝えている。「すごい人だなぁ」と思いますね。研究の仕方も「すごいなぁ」と思っていますけれども。
あと、ワトソンとクリックのワトソン。DNAの二重らせん構造を見つけ、それが持つ意味を的確に見抜いた人です。今になれば当たり前なことなのですが、あの時代にそれがひらめいたことがすごいと思う。
もう一人あげれば、研究者としての僕の師匠に当たる佐藤了という先生。(注:阪大蛋白研の名誉教授で薬物代謝の主役であるシトクロムP450の発見者として有名。故人)すごい先生だったんだけど、全然えらそうにしない。「研究している人間は上も下もない。教授よりも大学院生の方がすごいことを思いつくこともある。そういうことを大事にしなさい」と僕らは育ててもらいました。 - イ : たくさん尊敬していらっしゃる方がいるんですね!
先生が学生のときはどういう生活を送っていましたか?
- 吉 : 僕らの大学時代はね、今から45年以上も前なんだけど、今とは社会の状況がずいぶん違っていました。遊ぶ場所などはあんまりなくて、大学でクラブ活動をし、僕は下宿をしてましたから、下宿に友人たちと集まって、いろんな話しをするというような日常生活をしていました。僕が大学生だった頃と今とでは、18歳から22歳の集団の中で大学に通っている人の割合が違いますよね。妙な言い方だけど、当時の大学生達は、「自分たちは大学生なのだから社会の役に立つようなことをしないといけない」など、かなり生意気なことを考えていました。
今なら大学に行く人がほとんどだから、大学生になるのは普通ですよね。でも昔はずいぶん違っていて、「これから先に何をやるか」、「自分が生きていることの何が社会に役立つんだ」など、友達同士でギャンギャン言いあっていました。「今の政府はこれでいいのか?」というような学生運動も盛んな時代でもありました。僕が大学生だったのは、1961年~1964年ですが、その頃は日本が大きく変わりつつあった時代なんです。(注:1964年は、東京でオリンピックがあり、東海道新幹線が「夢の超特急」として開通した年。日本が高度経済成長を遂げたのは、その後の1970年代でした。) - イ : そうなんですね。
今は生化学をしていらっしゃいますが、元々は有機化学を勉強するのが好きだと聞いたのですが…?
- 吉 : そうですね。大学は家から離れたところに行きたいとは思っていて、高校の先生にどうせ離れるなら北海道まで行ったらと勧められ、北海道大学(以下、北大)に進学してしまいました(笑)それで、北大行ってから何をしようかなって考え(注:当時の北大は、学部別ではなく理類、文類などの区別で入学し、2年の後期に学部を選び、3年から学部に進むという仕組みでした。)、有機化学に興味を持ちました。農学部の中には農芸化学っていう学科があったし、1960年代は石油からいろんなものを作る化学工業が発達して、公害が起こり始めるちょっと前でしたから、工学部の応用化学科もいいか・・・などと考えていました。そしたら、所属していたクラブ活動の先輩に薬学の人がいて、すごい影響力が強い人だったのですが、「化学なら薬学。日本の有機化学は薬学が引っ張っているんだ!」と言われてそうかもしれないと思った。「薬学はいいぞ!」って言われたから、じゃあそっちにしようと思って(笑)、それで、医学部薬学科に入ったわけです。(注:当時、北大には薬学部はなく、医学部に医学科と薬学科がおかれていた。) 僕が薬学に進んだ時代は、ワトソンとクリックがDNAを見つけて10年経ち、生化学が急速に発展していた頃です。例えば、ミトコンドリア、今は高校の教科書に出てますけど、詳しい研究が始まったのは1962~3年くらいからなんです。そういった最新の話を授業で聞いていて「生化学って面白いんじゃないか」と考えはじめました。そして、卒論研究をやる研究室として選んだのが衛生化学。その当時、北大の薬学には生化学という研究室はなくて、衛生化学の教授が「衛生化学は、“衛生”に関する“化学”をやるのではなく、薬学の中で“生化学”を“衛”っている研究室なんだ。生化学をやるなら衛生化学」と誘われてそこに入った。素直だったのですね。(笑)
- イ : (笑)
- 吉 : 北大の薬学で私の周りにいた人たちは薬剤師になることを余り考えてはいなかったんです。むしろ研究者になるにはどうするかを考えてた。化学が面白いと思い、「化学をやるなら薬学に行け」って言われて薬学に進み、薬化学やろうかなって考えていたのに生化学が面白そうだと衛生化学に入り・・・・、薬学にいたのに薬剤師ではなく生化学の研究者に向かったのです。
授業で話しているけれど、今皆さんが受けている僕の授業の内容の多くは、僕が大学に入った頃より後にわかったことなんです。だから、僕が今教えてる内容はそれが分かっていく過程で自然に覚えたもの。何十年もかけて「あぁこんなことがわかった。こんなこともわかった。これは面白い・・・」って知識を積み上げてきた。でも、皆さん方は、2年生という19、20歳の年で、
あれだけの量のことをまとめて学ばなければならないわけで、「大変だろうなぁ」と思いますね。そういう意味ではあなたたちが生きてる今の時代と、私たちが大学生として生きていた時代とで、特に生物学などは、学ぶべき内容もずいぶん違いますね。 - イ : 大学でやりたいことがみつかったんですね。
武庫女生のイメージは?
- 吉 : 昨年広報室から報告されたアンケート結果で「武庫女のイメージは?」という問いに対する回答の1位が「おしゃれ」だった。これを見てびっくりして、「うそ~~っ」と思うんだけど(笑)どうですか? 武庫女の薬学生は、すごくマジメですよね。でも、いい意味での「やんちゃさ」が足りないと僕は思う。もうちょっと自分で自分の言いたいことを出してほしいなぁと思う。暗くはないけど、活発にしているんだけれども、マジメ。 それから、武庫女に限らないけど、みんな周りを気にしすぎる。人がどう言うかとか、どう思われるとか空気が読めないとか(笑)…空気が全然読めないのもよくはないけれども、読みすぎて黙ってしまうのもよくないなぁという気がしますね。
- イ : そうですね。
武庫女生へのメッセージは?
- 吉 : 「自分がこれから何をしたいのか」ということをしっかり考えてそれに向かって、勉強もそうだし、遊ぶ事もそうなんだけど、やってほしい。なんとなく「大学生」してますとか、なんとなく楽しく「女子大生」としての生活をしながら、薬学を学び続けるのはしんどいでしょう。薬学科では6年かけて薬剤師になる。だからその方向に向けて、人の「いのち」とか「医療」とかを考えてもらわなきゃいけない。
また、健康生命薬科学科の人も「別に私は薬剤師になりません。一般就職するから普通に女子大生で・・・・」と言ってしまってはちょっと情けないですね。「健康」や「いのち」を考える研究者や科学者になってもらいたいと思って作った学科ですから、そこで学ぶことで自分に何ができるのかというのをよく考えてほしいですね。
あと、「試験があるから、そのために勉強する」ようなことはしないでほしい。授業でも話していますが、大学での勉強はプロになるための訓練なんです。だから自分で自分の力を高めようと思って勉強することが必要です。それが積み重なって薬剤師というプロになる。あるいは健康や生命を研究できる人になる。だから、「試験のために勉強して試験で合格点取ったら終わり!」という勉強はしないでほしい。
これは特に武庫女生に限らず、全ての薬学生にぜひ伝えたいですが、自分達が人の「いのち」を扱うプロを目指していることを分かっていてほしい。薬剤師さんは薬の専門家です。薬剤師さんから薬の説明を受けるときに、薬剤師さんを信用しますよね。この人は「間違ったことを言っている」とは思わないですよね?だったら、間違ったことを言わないようにちゃんとした知識を身につけないといけない。そう思えば、試験のための勉強とはひと味もふた味も違う勉強ができるのです。
もうひとつ言わせてもらえば、薬学科には国家試験(以下、国試)というのがあります。でも、「国試~~!」という(それだけを目的にした)勉強するのはやめたほうがいいです。国試に通るのは当たり前のことで、国試合格は目的ではなくて通過点です。国試は、(先に話したようなプロとしての)力がつけば必ず通ります。それから、健康生命の方は、「薬」や「いのち」を研究するという基礎の部分を受け持つことになるのです。だから、薬学科の人たちのように、「薬があり患者さんがいて、いろんなことを幅広く身につけて説明する」薬のプロとしての資格ではなくて、「自分はここが得意なんだ」、「これに興味があるから深く研究したいんだ」という目標を見つけてほしいなぁと思います。また、健康生命の方は国家試験がないから、遊んでいてもいいんだということではありません。全てに対して平均して良い成績を上げなくてもいいので、好きなことは深く勉強してほしいですね。それが僕らの願いです。
受験生へのメッセージは?
- 吉 : 薬学部は資格を取るための学部だと思わないでください!資格の中で、薬剤師・医師・歯科医師・獣医師の4つの資格は(国家試験受験資格に関して)別格の扱いをされています。それは、資格を得るにはそれぞれに対応する大学の学部を卒業しなければならないということです。たとえば「管理栄養士」資格では、有機化学を○単位、生化学を○単位…全部で合計○単位とりなさいと資格単位が決まっていて、「資格に必要な単位をとっている」ことが条件ですが、薬剤師では個々の科目や単位ではなく「薬学部を卒業すること」が条件なのです。薬剤師など4つの資格は「いのち」を扱う専門家の資格なのです。「いのち」を扱う専門家は、単に必要な単位を修得していれば良いのではなく、大学の専門の学部で、それに向けた幅広い教育を受けることが求められているのです。だから、教養教育も必要だし、ヒューマニティも大事だし、もちろん自然科学も理解していないといけない。薬についての専門知識だけではだめで、そういったことを総合的に身につけている人に対して与えられる資格なのです。だから、動機として「薬学で学ぶというのは資格を取るため」というのはあるだろうけれど、このような他の資格との位置付けの違いを考えてほしいですね。
受験する人にわかっていてもらいたいのは、「医療をやるんだ」、「病気になった人、弱い人のために役に立ちたい」、だから、「いろんなことを勉強して薬剤師として活躍したい」という気持ちを強く持ってきてほしい。「薬学に入れば資格が取れて、結婚しても薬剤師さんだったらパートで働いても時給が高そう!」そんな目的だけで薬学部へ来られるとちょっと悲しいです。
あともう1つ高校生の方々に伝えたいことは、薬学で勉強すれば、「知識」や「技能」が身につきますけれど、医療に携わるときに大切なことは、知識とか技能を実践する「態度」なのです。分かり易く言うと、あることについて「知ってます」というのが「知識」、「こんなことができます」というのが「技能」です。そして、その2つを活用して実践するというのが「態度」なんです。だから、薬学で講義を受けて沢山の「知識」を学びます。実習ではいろんな「技能」を身につけます。薬剤師さんはそれだけではダメで、それを使って「患者さんのために何ができるか?」を考え、実践する「態度」、それが大変大事なのです。薬剤師になるのに、薬学部での教育が必要だとされているのは、そういった総合的な能力を養うことが求められているからなのです。そういうことをよく分かって薬学を目指してください。 - イ : アドバイスありがとうございます。
(2009年2月18日インタビュー)
